インプット過多になっているって言ってるそばからw
しょうがない。これが俺の生き方なんだ。目的ドリブンの思考法という本についてミノ駆動さんがたびたび紹介していて、kindle Unlimitedで読んでみることにした。目次からして、ちょうど求めている課題解決能力に加えて、今気にしているリーダーシップや、部下のモチベーションアップ向上と言った部分に効果があるといった文言が並び、興味を大きくそそった。
主な主張は他の本でもいくつか見たことがある。どちらかというとロジカルシンキングや、コンサル的な内容に近いように感じた。そもそも書いているのがデロイトの人ってこともある。目的を明確にしないと仕事がうまくいかない。これはここ最近のプロジェクトでもいくつも身につまされることである。一体何を目的としているのか。手段が目的と化しているなと速攻で思わされる今まさにやっているプロジェクトがある。
もう一つはっと思わされるのは、現状の延長線上にゴールがあるとは限らないという部分である。とはいえ明らかに、現状の延長線上で考えるのが早い。しかし現代において変化が急峻であり、この考え自体が危険というわけである。これはかなり難しく、現状の別次元に理想のゴールを設定したつもりでも、実はただの延長線上ということは多々ある。
また、副業についてよく考えることがある。これも一応その一環として始めているが、実績でいえばほぼゼロと言って過言でない。目的は数年以内に2億稼ぐことに対してなのであるから、スケールが違う。最近でこそここは目的を明確にしたが、ブログを作るのはなんとなくで足掛け20年くらいやっている気がする。ただし、今では稼ぐ手段としてなのではなく、アウトプットの場として活用している。現状はどう考えたって投資の額が大きすぎて、副業なら投資に力を入れるべきである。今回読んでいて、そもそも副業の目的が少し間違っているのではないかと思ってきた。
副業の私の中での目的の大きな要素として、本業でくいっぱぐれた時の保険という要素があったため、保守的でありながらとんでもな目標を持っていたが、本業でくいっぱぐれるというのを防ぐという意味では、本業がダメになったとしても別のところでやっていける能力を身に着けておいた方が手軽で現実的である。
そうでなくとも最近のプロジェクトでそういえばこのプロジェクトの目的って何だ?と思い自分の中で整理したうえで、プロジェクト終盤でメンバーに再確認するというクソプレイを行ったこともあった。幸い、合っていたが、違っていたらどうしたのだろうか。ただ、少しだけ手段が目的化していた箇所があり、今となってはいらないような気もするオプションをつけてしまった。その部分を検討する必要すらなければ100時間は楽に短縮できていた。
ぱっと思いつく事例だけでも私にとっては熟読すべき本であることがわかる。
背景と目的を明確にする
ひたすら「それの背景は?」と聞かれることが多かったが、課題の背景を相手がわからないと、目的があっているのかを正しく判断できない。背景が重要というのはそれはそうで、私はよくすっ飛ばしていたが、相手に伝わらないことが多々ある。説明資料冒頭には背景と目的をつける。これは心がけようと思う。口頭にしても、上司への相談とかであれば簡単な背景・前提くらいは説明したうえで相談しようと思う。
適切な目標を立てる
これがかなり難しく、最近はSMARTであるかどうかと言われる。達成可能かこれ?ということがよくあるのと、期限も決まっていないことが多い、定量的かどうか、測定可能かどうかもまあ頑張るって何を持って頑張ったのかとかよくある。何が最適解か、本を読んでもしっくりとは来ていないが、ロジックツリー的な感じで目的を要素に分解し、クリティカルに効くと思われる内容に対してそれを目標として立てるという理解でいる。実際、普通はそう目標を立てる気もするので、これをSMARTに飾ればいい気がしている。
適切な手段を選択する
これが簡単に思い浮かべば苦労はないが、ロジックツリー的なやり方でさらなる深堀をしていく。そして具体的に実行できるレベルの打ち手となるところまで掘り下げていく。そしてそれは目的を達成できるか。現実的に、簡易にできる方法が望ましい。
問題の見極め方
問題の見極めの項では、生産性向上というお題目について考えていた。生産性向上のための最大の問題というか阻害要因は、弊社ならば、生産性向上をしても残業代が減って、単位時間当たりの労力が増えて疲れる。これに尽きる。
結局、Udemyのロジカルシンキング講座で受けた内容とほぼ一致するが、ロジックツリーを作ってなぜなぜ分析を行い、腹落ちする内容になるまで行う。その後、重みづけてして、問題の本質を見極める。
組織のみんなの意見を聞きすぎて、とがりのない解決策になるか、内部で角が立たないように根回ししすぎてスピードが落ちるといったあるあるが示されていたが、あるある過ぎて悲しくなる。角が立つことを承知で実施するという話だが、弊社でそれをやることは現実的でないのも悲しいところ。
アナロジーな学習
知識を別の課題に転用するのをアナロジーというらしい。何がどう役に立つかわからないのは確かであるし、勉強する以上、他にも効きののある基礎的かつ本質的な内容から学ぶという方針に間違いはない。活用しうる形で覚える(ただの暗記でなく、転用を前提とするというか本質を理解するというか)ことが重要。という話だった。
整理整頓やロジカルシンキングとかそういった部分はあらゆるものに効いてくるので、この辺りを理解してマスターすることの重要さを再認識した。
総合すると本当に読む価値のある1冊だった。年度の目標の立て方の方針についてももはやこの本を参考にルール作ったんじゃね?というレベルにそのまま書いてあった。リーダーになった方向けの用の本であるように記載していたと思ったが、だれが見てもいいように思う。広くロジカルシンキング的な形で業務を効率よく進めていくための方法が書いてあった。
kindle unlimitedに含まれているので使ったことない人は使ってみてください。
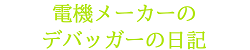
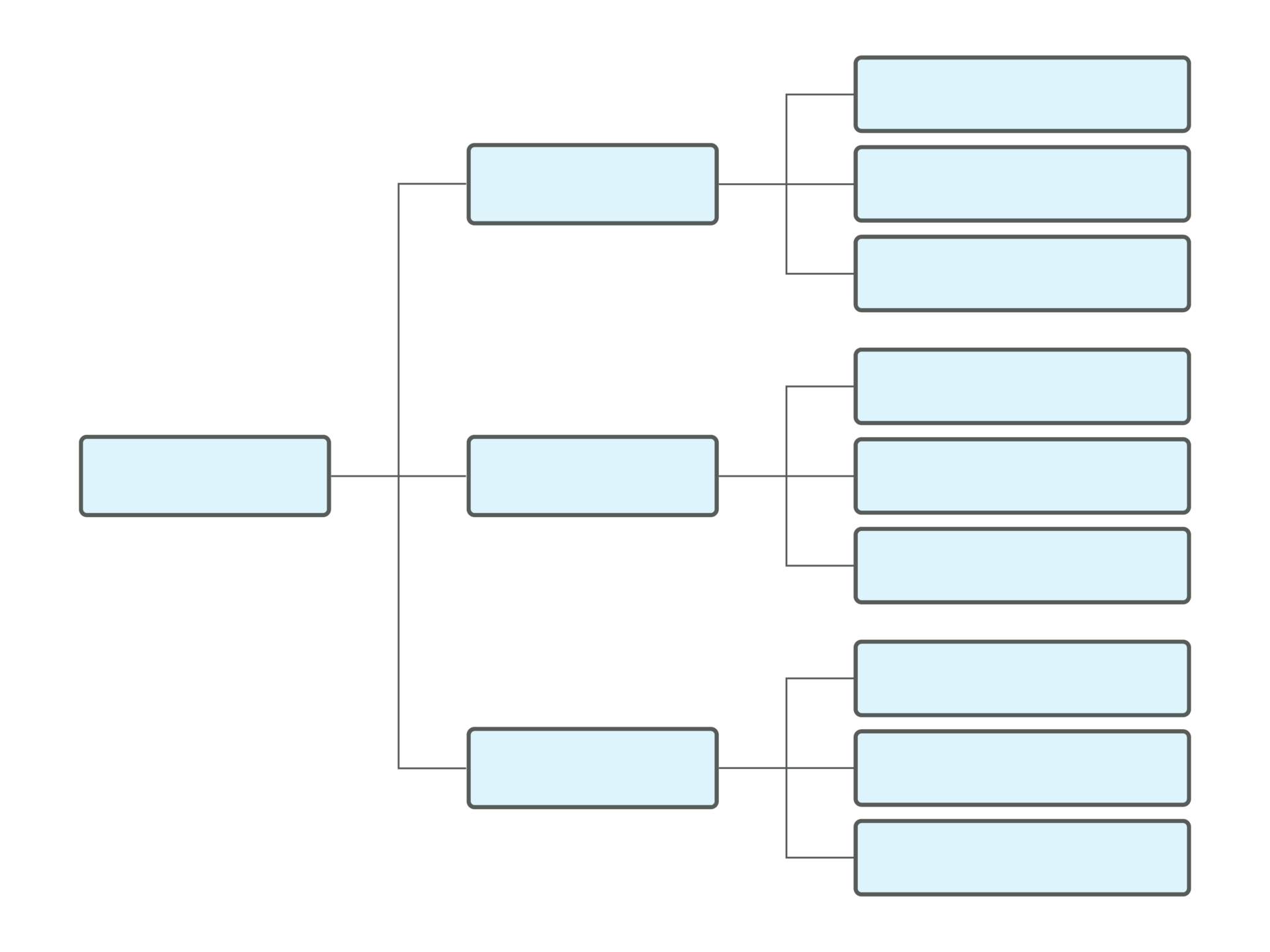
コメント