やりようあるか?
組織改善ができないほど腐り果てているということは書いた。じゃあどうすれば改善できるのかを考える。
再濃縮
掃きだめ部署ではあるが、掃きだめを目いっぱい集めて、最終処分施設と呼ばれる部署に送る。それ以外の人+新たに選りすぐった数人の中途採用で仕事を進める。また適材適所の人員配置を行うため年功序列というだけで上にいる人はその役を降りてもらう。その分給与も見直す。
個々で改善の余地のある人もいれば、改善の余地がないレベルの人もいる。さすがに見極めて処分していかないと始まらない。そうしないと周りが腐ったミカンになっていく。
最終処分施設のさらに究極版があるのだが、いいなあ…と本気で言っている我が上司がいる。ぜひとも送ってあげたい。
これ実施しない限り、業務を改善≒寄生虫どもが遊ぶか休む時間が増えるだけで、忙しい人は忙しいままになる。
書いてて思ったが無理だった。組織改善を謳うコンサルタントはこの状況から改善してみてもらいたい。
Chatgptさんに伺った
1. トップマネジメントのコミットメントとビジョンの明確化
- 率先垂範のリーダーシップ
経営陣や上層部が、現状の評価制度や業務プロセスの問題点を自ら認め、「働いた分が正当に評価される」「効率的な業務改善が組織全体の利益につながる」といった明確なビジョンを提示することが必要です。トップからの強いメッセージが、現場の意識改革への第一歩となります。- 変革の必要性を全員で共有
現状の評価制度が「やるだけ損」「効率化すれば給料が減る」という歪んだインセンティブを生んでいる現実を、データや具体例をもって全員に伝え、なぜ改善が必要かを共通認識として持つことが大切です。
2. 報酬体系・評価制度の抜本的見直し
- 成果主義・効率性を正当に評価する仕組みの導入
現在の「減点方式」ではなく、成果やプロセス改善、効率化に対してプラスの評価が得られる仕組みを検討します。たとえば、定量的・定性的な指標を用いた評価制度(KPI・OKRなど)の導入や、業務改善提案に対するインセンティブを設定するなど、働いた分だけ報われる環境を整えることが重要です。- 業務効率化が評価の対象になる文化づくり
効率化や業務改善が単に残業削減につながるのではなく、組織全体の生産性向上や顧客満足に結びつくことを評価軸に取り入れる必要があります。これにより、効率化を図った社員が「頑張っていない」と見なされるリスクを回避します。
3. 業務プロセスの見直しとタスクの再配分
- 雑務・非付加価値業務の削減
本来の業務に集中できるよう、現状の「雑務」や不必要な手続き、冗長なプロセスを洗い出し、整理・削減を進めます。業務プロセスの標準化と自動化、またはアウトソーシングの検討も有効です。- 業務の透明化と役割・責任の明確化
各自の役割や担当業務、成果が明確に分かる仕組みを整えることで、「やってる感」ではなく、実際の成果が評価される環境づくりを目指します。業務の見える化は、責任の所在を明確にし、不公平感を軽減する効果も期待できます。
4. コミュニケーションの活性化と意見収集の仕組み
- 現場の声を拾う仕組みの強化
エンゲージメントサーベイだけでなく、個別面談、フォーカスグループ、ワークショップなど、様々な形式で従業員の意見や不満、改善提案を収集します。特に「実際に頑張っている少数派」の声を拾い上げ、具体的な課題を特定することが肝要です。- フィードバックループの確立
集まった意見をもとにした改善策を実施し、その効果を定期的に評価・フィードバックする仕組みを作ります。改善が実際に現場に反映されることで、従業員のエンゲージメントが高まります。
5. 組合との協力と外部の視点の導入
- 組合との対話と共同改善の推進
組合は従業員の保護を目的としていますが、現状では変革への障壁にもなっています。組合と対話を重ね、双方が納得できる形で組織全体の生産性向上や働きやすい環境作りに向けた改善策を模索する必要があります。- 外部コンサルタントや専門家の活用
内部だけで解決が難しい場合、外部の専門家を交えて現状分析や制度設計の見直しを行うことも有効です。第三者の客観的な視点は、内部対立の緩和や新たな発想をもたらす可能性があります。
6. 長期的かつ段階的な改革計画の策定
- 短期・中期・長期の目標設定
一気に全てを変えようとすると混乱が生じやすいため、段階的な改革計画を策定します。まずは小さな改善から始め、成功事例を積み重ねることで、組織全体への波及効果を狙います。- 文化変革のための研修やワークショップの実施
従業員の意識改革を促すため、リーダーシップ研修やチームビルディング、業務改善ワークショップなどを定期的に実施し、組織文化の転換を図ります。
まとめ
現状の「やるだけ損」や「効率化すれば給料が減る」という風潮は、評価制度や業務プロセス、コミュニケーション、さらには組合との関係といった複数の要因が絡み合った結果です。
これらを一度に変えることは困難ですが、トップマネジメントの強いリーダーシップのもと、報酬体系・評価制度の抜本的見直し、業務プロセスの整理、そして現場からの意見収集と外部の知見の導入を組み合わせた多面的アプローチで、少しずつ改革を進めることが求められます。
また、短期的な改善だけでなく、長期的な視点で段階的に改革を進める計画を策定することで、持続可能な組織変革を実現できるでしょう。このような取り組みにより、真に「働いた分が評価される」健全な組織文化への転換が期待できます。
素晴らしい提案の為、このまま上層部に送りたいレベル。ただ、よく見ればそのほとんどは上層部は今まさに実施しているつもりであり、それがまさに逆方向に機能してしまっているんだなという意味で悲しくなっている。むしろChatgptに聞いているのかというレベルの施策の打ち方である。
なぜ逆方向に機能しているのか
上記1。多分やってるつもり。組合が強すぎる。
上記2。やってるつもり。実態はそれほど差異が出る報酬体系でもなく、定量、定性さは個人かクソ忙しい管理職に丸投げという驚異の体制
上記3。多分やってるつもりだが減ると困る勢力により業務は増えているし担当の完全な明確化等不可能で、中間のボールの方が絶対量として多い。明確化すればするほど中間のボールは誰も拾わなくなる。
後半部分は単発数百円レベルで渡されても残業10分くらいの価値しかない。根本的にスケールがおかしい。
上記4。施策のうちの1つが今回の件なんだろう。改善されては困る多数派勢力の意見を取り入れても意味がない
上記5。多分やっている。ただ組合が強すぎる。第三者意見を明確に聞いて責任を持って実施する上層部はおらず、自分の保身と昇進にしか興味のない犬しかいない。YouTuberにも言われていた。
上記6。多分やっているつもりかもしれない。明らかにやれていない。
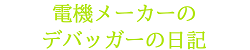

コメント