良書すぎる
久々に本屋に一人で立ち寄る時間ができたので、ソフトウェア関連の本を見て回った。その中で今すぐ私の業務にとって効果のありそうなタイトルである、ソフトウェアテスト系の本をいくつかぱらぱらとめくったところ、ソフトウェアテスト徹底指南書という本に気になる記述がたくさんあり、購入した。この本、著者の業務がソフトウェアテストというか私のような立ち位置に近い職のようで、俗にSETと呼ばれるものが一番近いように思う。(本人はテストエンジニア(SET含む)、QAエンジニアとして働いていると書かれている。)そもそもこの立ち位置が相当軽く見られているが、実際にはどれほど難しいのかということにも結構触れられていた。
この著者の井芹さんはトヨタ自動車でソフトウェア開発やQAエンジニアしていたり、現在はJSTQBの技術委員やコンサルされているようだが、それゆえに私が目指す姿に限りなく近いキャリアを持っている。弊社も漏れずJTCのため、同じような課題・悩みの解決について多数の記載があり、かなりうならされるものがあった。
何周か読みたくなるレベルだが、さわりで買うに至った記述
即買いを決めたのは2.6章品質マネジメントを担う部門の陳腐化 完全に弊社ですやんと思わされた。弊社関係者は全員この章読め。今すぐ100回読め。あとはpartⅢのテストの分析と実行。ここも漠然と経験から個人的にサービスとして行っていたソフトウェアテストの見積や、環境構築のボトルネックを早期に知らせたりと言った内容の必要性や手法が書かれていた。また、往々にしてテスト工程はスケジュールがタイトだが、そこに対する解決策が多数書かれていた(33.8章、33.9章)。前半の対策も納得の内容だが、最後の開発と仲良くというのも本当に重要だと思う。弊社無茶苦茶対立してて全然協力できていない部署が多々あり…開発がひたすら炎上してスケジュール通り終わらないを繰り返す要因となっている。開発部署と弊隣の部署でお互いリスペクトがない。まともにコミュニケーション取れていないのでそうはならんやろ…という手戻りが多数回発生する。何だったら心理的安全性の大事さも結構ボリュームを割いて別の章に記述されている。
他の部分もかなり網羅的な書籍になっている。早くこんな良書を知りたかった。と思ったが2025/06/28出版と相当に最近の書籍である。たまには本屋に行ってみるのも悪くないなと思った。
また読み込んでいきつつ記載を充実化する。
CPM法
テスト設計でこんな方式知らないわと思ったが、アンチパターンだそうで、確かに結構な頻度で遭遇し、非常に痛い目を見ることが多い。経験の浅い設計者が多用してきて、仕様書の末尾を変えてくるだけなので、いやだからそもそもそれをどうやったら実施できるのよ。てか分岐足りなくね?ということがここ最近も結構あった。テスト仕様書の作り方も容易に仕様書コピーして末尾にであることとつけただけ(これがCPM法を意味する)であることが想像できるのだが、そんな名前がついているとは知らなかった。また、テスト設計において、テスト実施手順をどこまで書くかという問題についてもうなる記述があった。細かく書くと保守や作成コストがかかるから、Q&Aや説明、フォロー含めて統合的なものにするというのは確かにある。ここで一つ上で書いたコミュニケーションがまともに取れていないとこの手法は崩壊する。また、序盤の経験値稼ぎ的な項目は詳細に書いて、後半の難易度高い項目は荒く描くというグラデーションもありと思う。弊社では全くの素人が読んでもわかるという思想の長大ドキュメント至上主義のため、だれもが見て理解することをやめ、編集する人や参考にせざるを得ない人が地獄を見るドキュメントが多数ある。
テストする側の視点で記述する必要というのは弊社でほぼ考えから抜け落ちていているように思う。何だったら最近もテスターでなく設計者が理解できる記述にしてと言われた。逆ぅ~
開発の高品質と高スピードの両立
下の本自体のタイトルの一部ではあるが、弊社(著者のトヨタ自動車ではない)では名目上品質最優先であり、スピードがガン無視されている感がある。高品質を保ちながらスピードを出すために必要なことで、私が速攻取り組めそう(取り組むべき)内容としては、単純な重複や、ねらいの品質に合致しない無駄なテストの排除、必要なテストの追加、テスト仕様書の早期作成。テスト容易性やテスト駆動開発を少しづつ浸透させていくということだろうか。とりあえず、この本を布教していきたい。

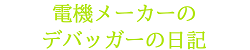

コメント